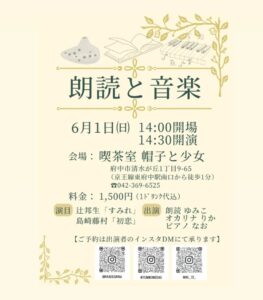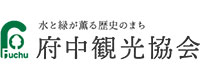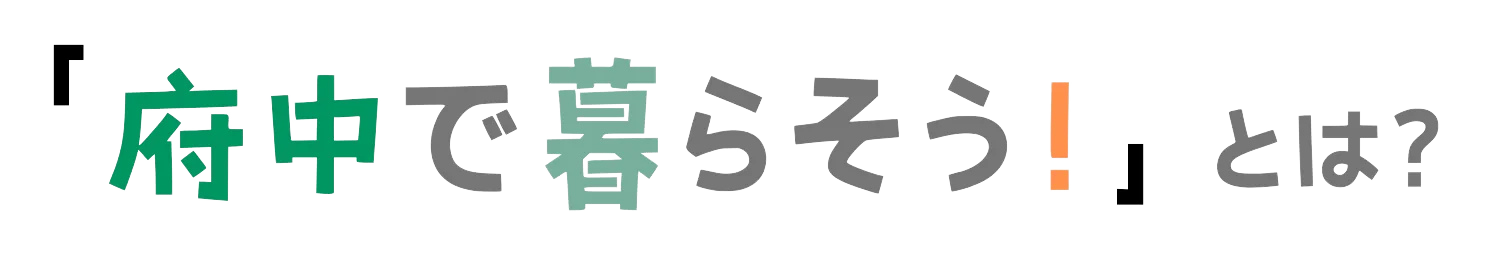本日2025年5月3日(土)18時30分からは、くらやみ祭りの名物のひとつである「囃子の競演」が執り行われます。その歴史と見どころについて、初めての方にもわかりやすくまとめましたので、ぜひお祭りを楽しむ上での前提知識としてお読みください。
「囃子の競演」とは何か?
府中市の大國魂神社で毎年春に行われる例大祭「くらやみ祭り」の中でも、5月3日の夕刻に実施される「囃子の競演」は特に人気の行事です。夕方6時半頃になると、神社参道横の馬場大門のケヤキ並木(旧甲州街道沿い)に約10台の山車(だし)が勢揃いし、各町内の囃子連が一斉にお囃子を演奏します。
笛・太鼓の音色に合わせて踊り手が舞う伝統芸能である府中囃子が、灯りに彩られた山車上で賑やかに繰り広げられ、祭りの幕開けを華やかに盛り上げます。都指定無形民俗文化財にも指定された「武蔵府中くらやみ祭」の見所の一つであり、地元の人々のみならず観光客にも人気のイベントです。
歴史的背景:古式ゆかしい祭りとお囃子の起源
囃子の成り立ちと流派について
大國魂神社の例大祭は約千年以上前、武蔵国の国府祭に由来するとされ、古代から人々に崇敬されてきた伝統ある祭礼です。「くらやみ祭り」の名の通り、江戸時代以降この祭礼は深夜に街の明かりを消した“暗闇”の中で執り行われていたため、その名が定着しました。神秘的な夜の祭として知られ、太鼓やお囃子の音だけが闇夜に響く厳かな雰囲気だったと伝えられます。
一方、現在のような山車とお囃子の形態がいつ頃から始まったかは正確には不明ですが、古くから祭礼の際にお囃子が奉納されていたようです。江戸時代になると町人文化の発展とともに、各町内で山車(移動舞台)を飾り付けて練り歩き、お囃子で祭りを盛り上げる風習が広まりました。府中囃子もこの頃に現在の形が完成したと考えられており、西部は「目黒流」、東部は「船橋流」という二つの流派に分かれて演奏する伝統が確立しました。
これら二流派の名称はそれぞれ発祥地の地名(東京・目黒と世田谷区の千歳船橋)に由来し、目黒流は賑やかさ、船橋流は優雅さが特徴とされています。こうした長い歴史と伝統を持つ府中のお囃子は、地元の郷土芸能として大切に受け継がれてきました。
受け継がれてきた歴史について
戦乱や社会情勢の中でも祭りは守り継がれ、第二次世界大戦中の1945年には一時中断されたものの、戦後には地元有志の尽力で復活し現在まで途絶えることなく続いています。
2020~21年には新型コロナウイルス感染症の影響で神事のみ執行され、山車や囃子の行事は中止される事態もありましたが、こうした困難を乗り越えて再び賑わいを取り戻したことからも、祭りと「囃子の競演」が地域にとってどれほど大切なものかがうかがえます。
ケヤキ並木で行われる理由と現在の形
ケヤキ並木という舞台
くらやみ祭りの舞台となる馬場大門のケヤキ並木は、府中駅前から大國魂神社の大鳥居へ続く参道沿いの象徴的な並木道です。樹齢数百年ともいわれるケヤキが左右に立ち並ぶこの道は、江戸時代には甲州街道の宿場町として栄えた府中の面影を残す歴史的景観であり、祭礼の際には古くから重要な役割を果たしてきました。暗闇の中で行われていた往時の祭りでは、提灯のほのかな灯りとお囃子の音を頼りに神輿や山車がこの並木道を進んだとされ、ケヤキ並木は祭りと切っても切れない象徴的な場所だったのです。
現在、「囃子の競演」はこのケヤキ並木通りを舞台に選んだイベントとして位置付けられています。広い通りいっぱいに山車を並べられるスペースと、駅や神社からのアクセスの良さもあり、観客が鑑賞しやすいことが理由の一つです。戦後、祭りの安全面や交通事情に配慮して深夜の行事が夕方に変更されるなど祭礼日程が見直された中で、5月3日の夕暮れ時にこの囃子共演を行う現在のスタイルが定着しました。
ケヤキ並木の自然の緑に囲まれた雰囲気の中で、各町の山車とお囃子を一堂に会して披露することで、祭りの伝統芸能をより多くの人々に楽しんでもらおうという趣旨もあります。日没前後の薄明かりと提灯の灯火が織りなす幻想的な光景は、ここケヤキ並木というロケーションならではの演出であり、歴史と風情を感じられる舞台として「囃子の競演」をより一層印象的なものにしています。
参加する囃子連と山車の特徴
「囃子の競演」に参加するのは、府中市内各町内会の山車とお囃子の一行です。
町ごとに異なる山車とお囃子
くらやみ祭り全体では東西合計22台もの山車が存在し、5月4日夜の山車巡行では市内各地の山車22台が旧甲州街道~ケヤキ並木一帯を練り歩きます。
一方、5月3日の囃子競演に登場するのはその中の代表的な約10台で、主に神社周辺の町内を中心とした山車が集結します。山車にはそれぞれ由緒ある町名が掲げられ、地区ごとに所有する山車が参加します。各山車には地元の囃子連(保存会)が乗り込み、太鼓、大拍子(おおびょうし)、笛、鉦(かね)など伝統的な編成でお囃子を奏でます。
東西二流派それぞれの演奏スタイル
府中のお囃子の大きな特徴として、前述した東西二流派の演奏スタイルの違いがあります。上記にもあるように、大國魂神社を境に西側の地域は「目黒流」、東側は「船橋流」と呼ばれるお囃子の流派を受け継いでおり、それぞれ微妙に異なる節回しやリズムを持っています。目黒流は小気味良いテンポで賑やかに盛り上げる調子が持ち味で、聞くだけで思わず体が動き出すような躍動感があります。一方の船橋流は優美で品のある音色と間合いを重視し、ゆったりとした中にも華やかさを感じさせる演奏が特徴です。競演の場ではこの二つの流派が互いに競い合うように交互に演奏を披露し、リズムの違いを感じ比べられるのも通好みのポイントです。
各山車の構造や装飾にも注目です。府中の山車は江戸系の彫刻で飾られた重厚な木造の屋台で、車輪が付いた移動舞台の上に囃子方が乗り込む形になっています。山車正面には精巧な彫刻欄間や提灯、幕などがあしらわれ、町ごとに意匠が異なります。中には江戸時代から伝わる山車もあり(製作年不詳ながら江戸期創建とされるもの)、他にも明治・大正期に作られ昭和や平成に改修されたもの、新たに平成期に新調されたものなど様々です。例えばある山車は明治初期に初代が作られ、平成2年に新調された経緯があり、また別の山車は昭和26年製作(昭和61年改修)といった具合に、それぞれ歴史を背負っています。こうした山車自体の違いも見比べると興味深く、古い山車ほど彫刻や金具に風格が漂い、新しい山車ほど彩色や照明が鮮やかなど、年代ごとの特色が感じられるでしょう。
登場するキャラクターについて
お囃子の演目は基本的に共通の「府中囃子」ですが、各囃子連によって微妙に音の強弱や囃し方(盛り上げ方)に個性があります。演奏に合わせて山車上や周囲で踊るひょっとこやおかめ、天狐(てんこ)などのキャラクターも、各町内から選ばれた子ども達や若者たちが担当しています。おかめ(福女の面)やひょっとこ(ひょうきんな男の面)を付けた子どもたち、白装束に狐面を付けた天狐役の踊り手などが、笛太鼓の軽快なリズムに乗って愛嬌たっぷりに踊る様子は、見ている人の心を和ませ笑顔にしてくれます。時には獅子舞も山車から飛び出し、観客の目前で舞を披露することもあります。
こうした演出も各町内ごとに工夫が凝らされており、「今年は○○町のひょっとこが元気だったね」などと見比べるのも地元では楽しみ方の一つです。実際、夜のケヤキ並木を歩いていると、あちらこちらの山車でお囃子が奏でられ、大小様々なおかめ・ひょっとこ、そして獅子舞が元気に踊っている光景に出会います。この賑やかな競演こそ、府中の祭りらしい活気に満ちた伝統芸能と言えるでしょう。
観光客向けの見どころ・鑑賞ポイント
「囃子の競演」の見どころについて
「囃子の競演」は、府中くらやみ祭りの中でも初日のハイライトとしてぜひ見逃せない行事です。その見どころは何といっても10台もの山車が放つ迫力ある生演奏の競演でしょう。同時に複数の山車から奏でられる笛や太鼓の音はまさに音の競演で、賑やかな拍子が重なり合って祭りのボルテージは一気に最高潮に達します。各山車がお互いに負けじと演奏を繰り広げる様子は、観客にも熱気と興奮を伝え、一帯が祭り一色のエネルギーに包まれます。「競演」と名が付いていますが勝敗を競うものではなく、伝統芸能を披露し合う場ですので、純粋にお囃子のリズムに身を委ねて楽しみましょう。
鑑賞の際のおすすめポイント
鑑賞する際のおすすめポイントとしては、できれば開始時刻より早めに現地へ行き、場所を確保することです。囃子の競演は5月3日の18時30分頃開始ですが、夕方になるとケヤキ並木通り沿道には多くの見物客が押し寄せます。道路脇にはロープが張られ観覧エリアが設けられますが、前列で見たい場合は開始1時間前には到着しておくのが安心です。特に写真撮影を狙う方は、明るいうちから場所取りをして三脚を構えている姿も見られます。
鑑賞スポットについて
観賞スポットとしては、ケヤキ並木通りの中央付近が山車の集結地点となるため臨場感がありますが、敢えて端の方で見るのも一案です。山車は18時過ぎ頃から順次この通りに引き出され並んでいくので、入口付近(府中市役所前交差点側)では山車が入場してくるシーンを間近で見られます。また反対側の大鳥居近くでは、背景に神社の門や提灯の風景を入れて雰囲気たっぷりに楽しめるでしょう。どの位置でもケヤキの大木に囲まれた空間でお囃子を聞けるため、音響的には通り全体が舞台のように響き渡ります。木々に反響する太鼓や笛の音を聞きながら、日本の伝統的なお祭りの空気を肌で感じてみてください。
夕方から夜にかけて移ろう空の色と、灯りに照らされた山車のコントラストも見所です。開始直後はまだ薄明るい中、山車の提灯に火が灯り始める頃合いで、次第に空が暗くなるにつれて幻想的なムードが高まっていきます。ケヤキ並木の青々とした葉と提灯の橙色の光、そして山車の囃子方の揃いの法被や白装束が織りなす光景は、まさに写真映えする美しさです。
混雑予想について
混雑状況としては、5月5日の神輿渡御がクライマックスとはいえ、この5月3日もかなりの人出になります。例年、祭り期間中の5月3日~5日は交通規制が敷かれ、周辺道路は渋滞が予想されるほどです。臨時駐車場も用意されないため、公共交通機関での来場がおすすめです(京王線府中駅やJR府中本町駅から徒歩ですぐ)。
競演会場でも人波ができるため、小さなお子様連れの方は迷子や転倒にご注意ください。とはいえ地元の警察やスタッフが安全誘導しており、地域総出でもてなしてくれる雰囲気がありますので、安心してお祭り見物ができます。
同日開催の「競馬式(こまくらべ)」
なお、「囃子の競演」が終わる午後8時頃からは、同じく5月3日の伝統行事である「競馬式(こまくらべ)」が旧甲州街道で行われます。暗闇の中で再現される古式ゆかしい流鏑馬のような神事で、馬が甲州街道を疾走する様子は迫力満点です。せっかくなら囃子の競演だけでなく、この競馬式まで続けて見学すると、一晩で府中祭りの醍醐味を存分に味わえるでしょう。
地元の声とエピソード
府中の「囃子の競演」は、地元の人々にとって誇りであり生活の一部ともいえる行事です。古くから各町内でお囃子の技が受け継がれており、子どもの頃から祭り囃子に親しんできたという市民も少なくありません。実際、夜の山車で奏でられるお囃子やひょっとこ・おかめの舞を見ると、子どもの頃の記憶がよみがえると語る人もいます。それほどまでにこの祭りは地元に根付いた存在であり、毎年GW(ゴールデンウィーク)の時期になると「祭りが来ないと春が始まらない」と感じるという声も聞かれます。地元参加者にとっては、一年を通じて練習を重ね準備してきた晴れ舞台であり、各町内の結束力が高まる機会でもあります。
過去のエピソードとしては、平成29年(2017年)に府中市市制施行70周年を迎えた際、「囃子の競演」会場の山車先頭にそれを祝う横断幕が掲げられました。例年にはない特別仕様に、観客から歓声が上がり、市の節目を皆で祝った思い出となっています。また、令和に入ってからは祭りの様子をSNSや動画サイトで発信する地元若者も増え、遠方から訪れる観光客との交流も生まれています。2022年以降、コロナ禍を経て祭りが再開された際には「待ってました!」とばかりに沿道を埋め尽くす人々で賑わい、改めてくらやみ祭りと囃子の競演が地域にもたらす活力の大きさが実感されました。
「囃子の競演」は、長い伝統と歴史を持つふるさと府中の郷土芸能そのものです。地元の人々は幼いころからお囃子の音に親しみ、この祭りとともに成長し世代を繋いできました。そのため訪れた観光客にも「ようこそ府中へ!」という温かな雰囲気が感じられることでしょう。ぜひ地元の熱気に触れながら、歴史あるお祭りの醍醐味を味わってみてください。きっと府中という町の文化と誇りが伝わってくるはずです。
おわりに
府中くらやみ祭りの「囃子の競演」は、歴史的背景といい、会場の雰囲気といい、参加する山車と囃子連の情熱といい、見所が尽きない伝統行事です。ケヤキ並木に響くお囃子の音色や躍動するひょっとこ達の舞いは、日本のお祭りならではの情緒と活気を存分に味わわせてくれます。
地元府中の人々が守り伝えてきたこの貴重な文化を、観光客として訪れる皆さんもガイドを参考にぜひ体感してみてください。府中の夜に鳴り響く笛太鼓の競演は、きっと心に残る旅の思い出となることでしょう。